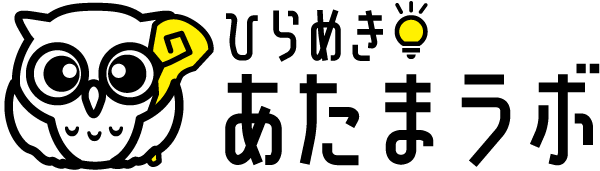福井市舞屋町にあるひらめきあたまラボは、パズルとボードゲームを通じて “自分の頭で考えることを楽しむ” 力を育てる教室です。「塾でも学校でもない第3の学び場」として、低学年のうちに“学び=楽しい”という感覚を根づかせることを目指しています。
小学校低学年こそ「遊びが学び」になる理由

探究心のゴールデンタイム
年長〜小3は、具体物を操作しながら概念をつくる時期。パズルやゲームは、仮説→試行→検証→振り返りのサイクルを自然に回す絶好の教材です。
正解が一つとは限らない世界
“答えが複数ある”状況に慣れることで、失敗を恐れず試行錯誤する姿勢が育ちます。こうした非認知能力は、教科学習の吸収率を高める土台にもなります。
ひらめきあたまラボと学習塾のちがい

| 視点 | ひらめきあたまラボ | 学習塾(一般例) |
|---|---|---|
| 主目的 | 思考力・非認知能力を伸ばす | 教科知識の定着・点数UP |
| 教材 | パズル・ボードゲーム・探究ワーク | 教科書準拠テキスト・演習プリント |
| アウトプット | 話し合い・プレゼン・作問 | 答案用紙・小テスト |
| 対象学年 | 年長〜小6(低学年歓迎) | 小4〜中高生が中心 |
| 低学年の授業形態 | 全て集団 | 低学年は個別 |
低学年向けコース
ひらめきキッズラボ(年長〜小6)
ひらめきパズル、抽象化ゲーム、作問体験で“考えるって楽しい!”を体感
高学年ではちょっと難し目の問題を、パズル感覚で楽しみながら解いていく。
ボードゲームラボ
協力・対戦・生産系など多様なゲームで、計画性や社会性を育てる。
高学年に行けば行くほど、運の要素よりも、計画性と戦略性が高いゲームになる。
小4までに身につけたい“考える道具”
- 図形感覚と空間把握
パズルで“回転・反転”を体験→中学数学の作図・証明に直結。
- 数量感覚(かたまり思考)
手順や得点の定量、推測。抽象化への入口。おおよその量を感覚的に捉える力。
- 言語化と説明力
自分の手番を行動と言葉で説明→作文・国語記述の基礎。
これらはテキスト演習だけでは習得しづらい領域。
遊びの中で手と口と頭を同時に動かすことで、学習塾の授業が“わかる→使える”に変わります。
福井の学習塾事情とラボ併用のススメ
福井県は全国学力テストで毎年上位に入り、個別指導・集団指導ともにハイレベルな学習塾が豊富です。演習量の確保や最新受験情報の提供では、塾は心強い存在と言えます。
一方で、低学年や中学受験を予定していないお子さまの場合、過度な先取り学習が「学校の授業はもう知っているから退屈」という状態を招き、学習意欲を下げることもあります。
そこで “学びのベース” を広げる場 として、ひらめきあたまラボのような思考力特化型教室が生きてきます。
また、ある程度の点数は取れる力はあるけど、難しい問題になると極端にできなくなってしまう方などにも、非常に良いのではないかと思います。
| 学習シーン | 目的 | 得られる力 |
|---|---|---|
| 週1〜2回 ラボ | パズル・ボードゲームで探究心を刺激 | 初見問題対応力/論理的思考/表現力 |
| 週1〜2回 塾 | 計算・漢字・基礎演習+受験情報フォロー | 定着力/テスト得点力 |
| 家庭学習 | 学校宿題+興味テーマのアウトプット | 自学習慣/主体的探究力 |
この3本立てなら、
- 「点数に直結する力」(=塾と家庭学習で養う基礎・演習量)と
- 「将来伸びる力」(=ラボで育む思考スキル・学びの楽しさ)
をバランスよく伸ばせます。
中学生になる前に「学び=楽しい」をインストール

小5・小6になるとテスト範囲が広がり、「覚える勉強」が急増。
中学では、これまで習ったことや、応用が徐々に増え、一見難しいと思う問題も多々出てきます。
中学での挫折を防ぐには、それ以前に「自分で考えて解けた!」という成功体験を積み、自分で考えるコツをつかむことが最重要です。
ひらめきあたまラボでは
で、自己肯定感と挑戦意欲を高めます。
まずは体験!無料体験のご案内
体験や相談について遠慮なくご相談ください。
1.親子で実際プレイするボードゲームを丸々体験
2.キャンペーン期間中の複数回の無料体験
3.お友達と一緒に体験
お問い合わせは下記にて遠慮なくお問い合わせください。