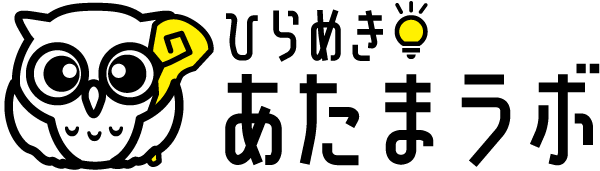福井県・高志中学校入試を「社会人目線」で読み解く1
会社員時代、採用面接に立ち会っていた頃、最後に差がつくのは「説明できるか」でした。
つまり、質問に対して自分の考えを、相手が理解できる順序で話せるか。
——高志中の入試問題を読むと、同じ素地を確かめていると感じます。
中学合格はもちろん大切ですが、これらを将来も使える力として鍛えることこそ、受験の本当の価値ではないでしょうか。
本稿では、福井で学ぶ子どもたちにとってのメリットと注意点、そして活かし方を、保護者の皆さんと共有します。
この記事の目的
塾の先生ではなく、一企業人の視点から、高志中入試を「合格」と「その先の成長」の両面で捉え直します。
記事は次の3部構成です。
- 第1部:高志中入試は何を測っているか(筆者の分析)
—— 読解・言語化・資料読解の三力と、短期(得点)/長期(成長)の違い。 - 第2部:なぜ受験するのか
—— 福井ならではの事情、合格のメリット、リスク、親子の合意形成。 - 第3部:受験をツールにする方法
—— 言語化習慣、家庭での実践、ひらめきあたまラボの取り組み。
目次
- 第1部 高志中入試は何を測っているか
- 1-1. 最重要は「文章読解力」
- 1-2. “言語化・表現力”は短期は代替可、長期は成長の核
- 1-3. 図表・データ読解は“目的を掴む”と楽になる
- 第2部 なぜ受験するのか(福井の事情と合意形成)
- 2-1. 企業人事の視点から見たメリット
- 2-2. 人気の背景とリスク(難度・精神的コスト)
- 2-3. 親子で共有したい目的設定
- 第3部 受験をツールにする方法
- 3-1. 学び方を変える「言語化」習慣
- 3-2. 家庭でできる実践ステップ
- 3-3. ひらめきあたまラボ:Show and Tellの発展形
- 3-4. まとめ:親子で話し合いたい3つの問い
1-1. 最重要は「文章読解力」
- 高志中の問題はとにかく文章量が多い。小学生には骨の折れる分量ですが、語彙力と想像力があれば読み解ける設問が多いです。
- 算数・理科・社会でも、淡々と事実が記された文章や資料を正確に読むことがスタートライン。読めればパズルを解く感覚で解ける問題もあります。
- 知識がなくても読解で突破できる設問が多いのも特徴。ただし、飽きずに読み切る集中力も必要です。
1-2. 「言語化・表現力」は短期は代替可、長期は成長の核
言語化とは、読んで理解した内容や解法の筋道を、(1)目的 → (2)根拠 → (3)手順 → (4)結論 の形で、だれが読んでも再現できる日本語にして外へ出すことです。
- 算数なら:「何を求める?→ どの性質を使う?→ どの順で計算?→ だから答えは○」
- 記述なら:「設問が問う軸は何?→ 本文根拠はどこ?→ どの順で述べる?→ だから私は○と考える」 この“外化→再現”ができると、思考の抜けや矛盾に自分で気づけ、ミスの再発も防げます。
短期的には、言語化は意識しなくても点数は取れます。しかし、それで片付けるにはもったいない内容であり、ここは誤解が出やすいので整理します。
- 短期視点(=試験の点数)
雰囲気を読むのが得意な子/違和感センサーが鋭い子、あるいはパターン暗記やテクニックが巧みな子は、言語化を明示的に行わなくても解けてしまうことがある。
実際、図形問題や定型的記述なら、雰囲気&経験値で正答に届くケースは存在します。 - 中長期視点(=学力の再現性・応用力/社会人基礎力)
言語化を怠ると、- 再現性が低い(ひねり問題で崩れる)
- 説明責任を果たせない(面接・記述・口頭試問で“なぜ?”を問われると弱い)
- 学びの蓄積がしにくい(思考プロセスを振り返れず改善できない)
- 応用・転用が効かない(他教科・実社会の問題解決につながりにくい)
つまり: 「必須ではない場合もある」が「やっておくと伸びしろが大きい」。
目的のタイムスパンが違うだけで、考え方が変わる。
試験をあくまで通過点と位置づけるなら、今のうちから「思考を外化→検証→改善→再利用」する習慣を持つほど、後の伸びしろは格段に大きくなります――これは採用・人材育成を担当してきた私の現場実感です。
問題の例
● 図形問題の例
- 言語化型:求めるのは「A形+B形−C形=D形」。
だから、まずAとBを出し、次にCを…という手順を言葉にして外に出す。その過程で “本当にCを引くのか? 共通部分は?” と検証もしやすい。 - 雰囲気型:与えられた数字を“だいたいこんな感じ”で当てはめ、経験則で計算。
うまく当たれば速いが、外れたときに戻る道筋が見えない/説明できない。
● 記述問題の例
「あなたの意見を書きなさい」
- 聞かれている“軸”はAか?
- Aを考えるにはBとCの関係、その課題は?
- 原因Dは何をしている? …という論理展開を言葉にできると強い。雰囲気読みが上手い子は“それっぽい”答案で得点することも可能だが、深掘りや再現性には限界がある。
仕事では目標や数値、指示の意味を解釈し、他者に説明し、合意形成する場面が日常茶飯事です。
後の成長に大きく影響があるからこそ、点数のためだけでなく、思考を外化→検証→改善→再利用できる“言語化習慣”を、あえて身につける価値があると考えています。
※少し話はそれますが、令和5年度《適性検査1- 3(2)》の“意見を2群に分類しグルーピングする”設問は、非常に仕事の力を測るには良い問題です。グルーピングや抽象化ができると、仕事でも課題の本質が見つけやすくなります。この力は普通の勉強ではなかなか身につかないと思います。
1-3. 図表・データ読解は“目的を掴む”と楽になる
- 図・表が何を示しているのか、その「目的」を掴めば理解が早い。慣れが必要ですが、読解と言語化に比べると優先度は下がります。
- 「この図表は何のために置かれている?」と自問する癖を付けると、必要な情報だけを拾うスピードが上がります。
プレゼンなどで図表、グラフを作る方に回ると、目的を掴みやすくなります。
もちろん算数や理科、社会では図やグラフ、表が出てきますが、どのような図、グラフ、表を作るか事前に最適なものに誘導されるため、なかなか成長しづらい点でもあります。