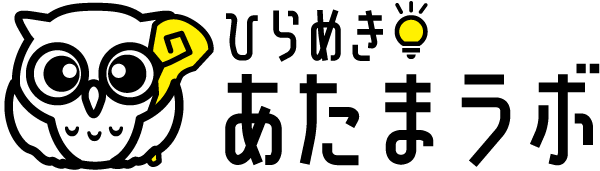福井県・高志中学校入試を「社会人目線」で読み解く2
こちらは3部構成となっています。
- 第1部:高志中入試は何を測っているか(筆者の分析)
—— 読解・言語化・資料読解の三力と、短期(得点)/長期(成長)の違い。 - 第2部:なぜ受験するのか
—— 福井ならではの事情、合格のメリット、リスク、親子の合意形成。 - 第3部:受験をツールにする方法
—— 言語化習慣、家庭での実践、ひらめきあたまラボの取り組み。
第2部 なぜ受験するのか(福井の事情と合意形成)
2-1. 企業人事の視点から見たメリット
高志中に合格する最大のメリットは、高志高校への進学が事実上約束される点です。
採用の場では、「どの高校を出ているか」が大学名以上に評価材料になる場面があり、福井で就職する際、“高校名”は想像以上に効きます。
特に福井では、藤島・高志・武生といった進学校出身者は、「中学時代から勉強してきた」「基礎学力・学習習慣が整っている」という共通認識がありました。大学名だけだと推薦・AOなど多様な入学形態があり、学力を一本で測れないケースがあるためです。
また、進学校出身者は勉強するという行為に慣れていることが多く、社会に出てからの学び直しにも抵抗が少ない傾向があります。そう考えると、中学受験で高志中へ入ってしまう価値は大いにあるでしょう。
ただし、この話は数年先には少しずつ変わっていくと考えています。
今の学力や経歴から見る採用から、これからの社会では、何が好きか、何を学んで来たのか、何をしてきたのか、何ができるのかを見られる時代がやってくるという点は考えておいたほうが良いかもしれません。
「好き」なことを突き詰めている人は、それだけで以下の力が見えてきます。
- 探究心:深掘りする過程で自分なりの問いを持つ
- 忍耐力:壁にぶつかっても続ける力
- 主体性:誰に言われずとも自ら取り組んできた
- 発信力/共創性:他者と共有したり成果を発信したりする傾向も
これらは、これから起こる不確実性の高い社会に必要な非認知能力と一致しています。
好きを形成する小学生時代を、どう過ごすかが大きく重要な時代になるでしょう。
2-2. 人気の背景とリスク(難度・精神的コスト)
福井では首都圏ほど中学受験が浸透しているわけではありませんが、高志中の人気は高いです。
背景には、
- “上位高校”に入るチャンスを2回得られる(中学→高校の2段階)
- 地元中学の学力水準に不安を感じる保護者心理
- 独自カリキュラムへの魅力
一方で、問題は難しいため読解力がない子にとっては苦痛になり、目的を見失うと、
- 精神力の浪費
- 失敗時の大きな敗北感
- “負の感情”の蓄積 といったリスク
が考えられます。
だからこそ、「なぜ受験するのか/しないのか」を親子で共有することが最重要です。
2-3. 親子で共有したい目的設定
- 受験の目的は何か?(合格だけか、力をつけることか)
- もし合格しなかったら?(それでも価値ある時間にする条件は何か)
- 子どもが納得しているか?(親発の目標になっていないか)
受験しない選択でも、高志中入試レベルの問題に取り組むこと自体が“良い勉強”です。試験問題は、将来に必要な力を見据えてよくできているので、ツールとして活用するのは“アリ”だと考えます。
ただし、前述の通り、通常の小学校のテストに比べて難しいため、目的をしっかりと持つ必要があります。