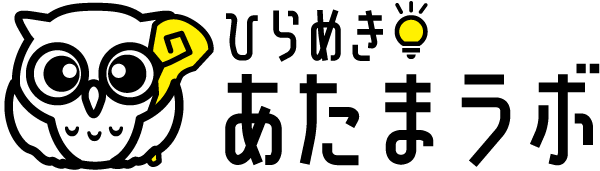福井県・高志中学校入試を「社会人目線」で読み解く3
こちらは3部構成になっています。
- 第1部:高志中入試は何を測っているか(筆者の分析)
—— 読解・言語化・資料読解の三力と、短期(得点)/長期(成長)の違い。 - 第2部:なぜ受験するのか
—— 福井ならではの事情、合格のメリット、リスク、親子の合意形成。 - 第3部:受験をツールにする方法
—— 言語化習慣、家庭での実践、ひらめきあたまラボの取り組み。
目次
第3部 受験を“ツール”にする方法
3-1. 学び方を変える「言語化」習慣
塾の立場ではどうしても「合格=成果」となるため、テクニック重視の指導が主流になりがちです。その結果、
- パターンで乗り切る→本質的な学びを逃す
- 形だけ覚えて合格→“使える力”が身につかない という“もったいない”事態になりやすい。
言語化を意識するだけで、学び方が変わります。
仮に高志中へ進学しなくても、価値ある時間になります。
3-2. 家庭でできる実践ステップ
- 読む前に目的化:「この文章や図は何のため?」を一言で決める。
- 根拠を声に出す:答えを書く前に、「根拠A→判断B→結論C」を口頭で言う。
- ミスの言語化:間違い直しは「どこで、なぜ、次どうする」をメモ化。
- 面接を想定:意見問題は必ず「反対意見」と「反証」も作る。
3-3. ひらめきあたまラボ:Show and Tellの発展形
ひらめきあたまラボでは、子どもたちが
- 自分の好きなものを分析し、
- 言葉でまとめ、他者に説明・プレゼンします。

アメリカの幼稚園で行われる“Show and Tell”を、小学生向けにレベルアップしたものです。
背景・特徴・理由を整理し、「こういうところが良くて、だから好き」と明確に言えるマインドづくりを目指しています。
これは入試問題の“言語化訓練”と直結しています。好きなもの×言語化は、最強の学びの入口です。
もちろん、好きなものだけでなく、様々な議題に対して自分の意見を自由に語ることを日々のクラスで大切にしています。
3-4. まとめ:親子で話し合いたい3つの問い
- この受験(勉強)で、子どもは何を得たい/得られる?
- 合格しなかった場合でも、価値ある時間にするには何を意識する?
- 今しかできない“好き”を見つける・語る機会を、どう確保する?
受験は終わりではない。学んだことをどう使うかを、親子で対話し続けてください。人生は長い。今しかできないことを楽しみ、好きなものを見つけ、語れる人になりましょう。
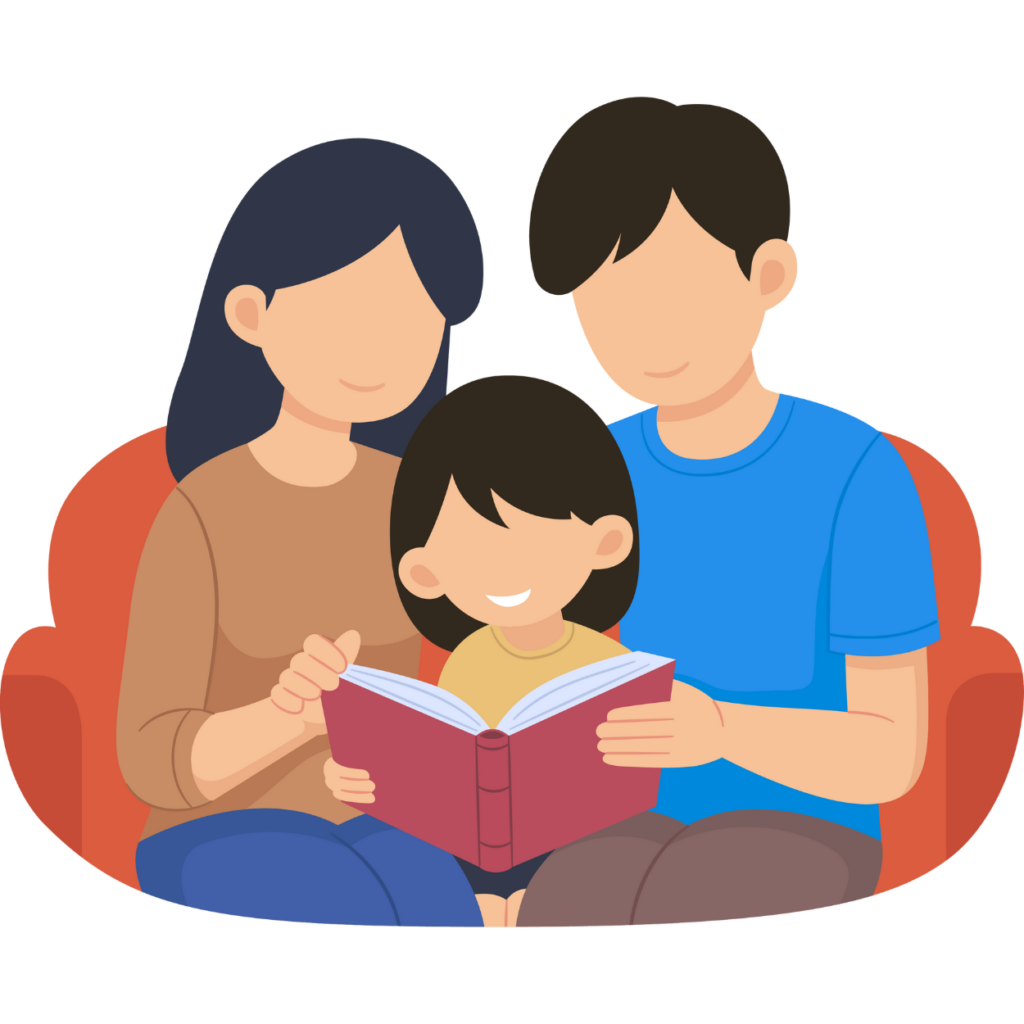
最後に
社会の入り口に立ってみれば、受験や偏差値は「評価軸の一つ」にすぎません。
それよりも、問いを立て、自分の言葉で考え、人と協働しながら学び続ける姿勢が試されます。高志中の適性検査は、その力の片鱗を測ろうとしていると私は感じています。親子で“学びの意味”を語り合うきっかけになれば幸いです。